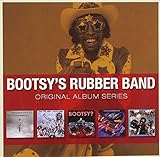ここではネタばれというかネタばらしとして、マンガの中で使っている元ネタについてちょっとお話しします。今回は第18話「ブーツィさんの秘密 パート2」です。
ブーツィー・コリンズの身上は【ネタばれ】第6話「ブーツィーさんの秘密」に詳しく書きましたので良かったら御覧ください。
JB’sからPファンクへの道程

ファンクを語る上で欠かせない独特なベースを類い稀なるリズム感で奏でるブーツィーは、1971年にジェームス・ブラウン氏の元を離れます。
実は、ブーツィーがJBとともに活動した期間はほんの一年強だけなのです。
その脱退に関するエピソードは、諸説あります。
ブーツィーがドラッグをブリブリにキメた状態でステージに立ち演奏していたとき。
幻覚でベースがヘビに見えてしまい恐怖で逃げ出してしまったところ、ジェームス・ブラウン氏の逆鱗に触れてしまいそのまま解雇された、という説。
もっと自由に、自分の中から溢れ出る音楽を思いのまま表現したいという願いから束縛まみれのJBバンドから去った、という説。
まあ、たぶんそのどちらも正といえるでしょう。
とはいえブーツィーがもともとジェームス・ブラウン氏に強い憧れを持っていたのは、JB楽団に参加する前からJBの曲をこなせたということからも間違いありません。それほどリスペクトしていたけれども、いざ行動をともにしてみるとハードで嗜好に合わなかった、ということなのでしょうね。
こうしたシチュエーションは、日本の就職活動でもよく見かける光景ですね。入社前は働くことや企業そのものに憧れ、やる気満々で入社するものの、すぐに現実を知り、落胆し、早期退職…
話が逸れました。
兄キャットフィッシュ・コリンズとともにJB楽団を抜けたブーツィー、そのままあのPファンクに参加するものと思いきや、デトロイトで「the house guests(ザ・ハウス・ゲスツ)」というバンドを自ら結成しています。
ハウス・ゲスツもリリースがあります。
この曲は71年リリースのため、ハウス・ゲスツ結成後すぐにシングルを切ったということになります。
ある日、Pファンクの総帥ジョージ・クリントンが、イベント・ブッキングの仕事をしている友人のマリア・フランクリンの家にいたときのこと。このマリアがオーガナイズしたライブをジョージが見に行ったところ、そこにはジェームス・ブラウン氏の圧政から逃れて伸び伸びとやりたい音楽に興じているブーツィ・コリンズと、彼が率いるハウス・ゲスツの姿が!
ドラッグの影響を受けたサイケデリックとも言えるファンク(ブーツィはJB楽団在籍中の容姿からも何となく想像つきますが、ジミ・ヘンドリックス大好きです)を志向していた両名は意気投合し、ジョージ・クリントンのオファーを受けてファンカデリックのベーシストとして参加を決意しました。
ジョージ・クリントンいわく「ブーツィは申し分なかった。ゴリゴリのファンク、アホなラブソング、なんでも最高にこなしてみんなを惹きつける魅力をもっていたんだ」そうです。
ブーツィーズ・ラバー・バンド
やがてブーツィーはPファンクの活動と並行して再び自らのバンドを結成します。「ブーツィーズ・ラバー・バンド」といいますが、このバンド名を直訳すると、なんと「ブーツィーのゴムバンド」です。
恐るべきことに、これはマジなダジャレであり、「バンド」は楽団という意味だけでなく、あの伸びるゴムバンドとも掛かっているダブルミーニングなのです。ラバーという名は彼らがラバースーツに身を包んでいるからではなく、まるでゴムのように伸びのあるファンクを演奏していたということに由来しています。
Pファンクはサイケデリックで宇宙的な世界観に満ちていますが、中でもこのブーツィズ・ラバー・バンドの楽曲は例えるならば快楽に悶える女体を想起させるような卑猥なグルーブ、官能的でエロティックな魅力で溢れています。その艶めかしい肢体のうねりとブーツィのベースが見事にイメージとして合致し、まるで幻覚かのように目に見える音楽を体現しているのです。
このバンドにはJB’sの屋台骨フレッド・ウェズリーと荒くれ者のメイシオ・パーカーまで参加しており、ジェームス・ブラウンの流れを汲んだ彼らがここまで狂ったサウンドを生み出したことには驚きを隠せません。
サンプリングソースとしてのPファンク
彼ら60年代からのレジェンドたちが、その30年後に西海岸のギャングスタラップ「Gファンク」の根源となったことはよく知られています。かくいう私も15年ほど前、ジェームス・ブラウン氏を聴く前にブーツィーやPファンクから聴き始めています。ドクター・ドレーを筆頭に、Pファンクを多数サンプリングしたイカツイ楽曲群に神経をやられ、その元ネタを知りたいと思って調べた結果でした。
無論、ジェームス・ブラウン氏自身もサンプリングソースとしては圧倒的な存在感を誇りますが、やはりタフでマッチョなガチファンクは、当時の私にはけっこうドギツすぎて入りにくかったんですね。
それが今やこんなマンガ描くほど好きになり、それが高じて彼の育った街オーガスタを見に行くほどになるのですから人生はわかりません。
おしまい。