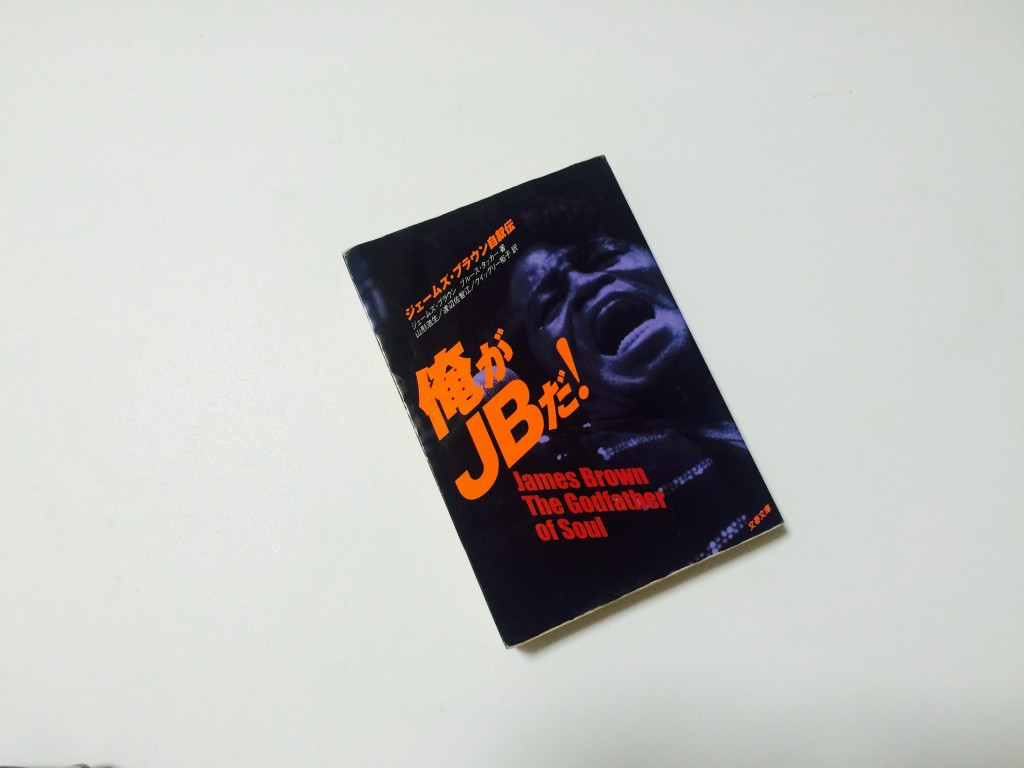「俺は七十五パーセントがビジネス、二十五パーセントがエンターテイナーだ」
(引用:JB論)
ザ・ハーデスト・ワーキング・マン・イン・ショウ・ビジネス(ショウビズ界で一番の働き者)と呼ばれたジェームス・ブラウンの言葉です。
ジェームス・ブラウンは自分自身を、アーティストとしてよりもビジネスマンとして捉えていたことが、この言葉からわかります。
彼がビジネスマンとして成し遂げた数々の偉業…いや、偉業だけでなく、理想の実現に向かって諦めることなく挑み続けるその姿こそ、数十年の時を経て今を生きる皆さんの心に深く突き刺さるはず。
彼はなぜ、目の前に立ちはだかる困難を打破し続けることできたのか。
彼の残した名言とともに、その理由の一端を覗いてみましょう。
「俺は客にジェームス・ブラウンの公演を特別なものだと感じてほしかった」
彼の1956年のデビュー曲「Please,Please,Please」。当時の彼が所属していたレーベルの社長シド・ネイサンは、この曲のデモを聴いて激怒してしまいます。こんな懇願するだけの曲が売れるか! と。
しかしジェームス・ブラウンは彼の怒りに屈することなく、「Please」のヒットを信じ、リリースするよう説得しました。もちろんジェームス・ブラウンの力だけではなく、プロデューサーのラルフ・ベース氏による「この曲は売れる!」という強い後押しあってのリリースだったそうです。
結果、「Please,Please,Please」はR&Bチャート6位の大ヒットとなりました。
…さて、それから数年後の1962年。「Try Me」のヒットで人気を確立しつつあったジェームス・ブラウン氏は、いよいよショウマンたちの聖地アポロ・シアターで単独公演を行うことになります。そこで、アポロのショウを録音し、ライブ盤として発売することをレーベルに提案しました。
しかし、またしてもシド・ネイサンの猛烈な反対に遭ってしまいます。
当時ライブ盤は「売れない」というのが業界の定説でした。「キレイな音で、楽曲をきちんと収めたスタジオ盤があるのに、なぜわざわざ歓声や拍手などの<雑音>が入った音質も良くないライブ盤を買うやつがあるか」、それが一般的な認識でした。
そこでジェームス・ブラウンは大きな賭けに出ます。
このライブ盤の録音にかかる費用は、すべて自分で負担する。費用はおよそ4000ドルにものぼったといいます。
自腹ゆえに気合いの入り方も尋常ではありません。バンドメンバーはもちろん、アポロのスタッフにも衣装を用意するなど趣向を凝らし、観客のテンションを上げることにアイデアを尽くしました。
「俺は客にジェームス・ブラウンの公演を特別なものだと感じてほしかった」
そして翌年リリースされた「Live at the Apollo」は大ヒット。それを機に業界の固定観念は「ライブ盤は売れる」にチェンジし、それは今でも変わらずに残っています。
俺は靴磨き小僧であり、刑務所に入った前科者であり、用務員であり、七年生に満たない教育しか受けていない。
ジェームス・ブラウンは立ち止まりません。
「俺は生き残りたかった。俺は靴磨き小僧であり、刑務所に入った前科者であり、用務員であり、七年生に満たない教育しか受けていない。こんな前歴の持ち主にそんなにたくさんのチャンスが来るもんじゃない。それが現実だ。」(JB論より引用)
そんな彼が次に着目したのが、自身のメインビジネスである「ショウ」の構造でした。
当時のアメリカにおいて、アーティストが興行を行うときには、各地方にいる本職のプロモーターと契約し、会場の確保や集客や宣伝を代行してもらいます。プロモーターはショウを仕切り、売上から莫大な金額のギャラを引っこ抜きます。アーティスト側に保障されていたのは、最低限の金額だけだったそうです。
良く言えば、あまり上手くいかなくても最低限の金額は得られる。しかし逆に、ショウが大成功したとしても、アーティストは相応のギャラを得ることができなかったとも言えるのです。
ジェームス・ブラウンは、リスクを負うことを決めました。プロモーターに依頼せず、自分たちで企画することにしたのです。
プロモーターの代わりに、地方での集客や宣伝には、地元の若いDJたちの協力を求めました。
当時DJたちは安い給料でラジオ局に雇われていました。アーティストやレーベルは、ラジオで自分たちの曲をかけてもらうためにDJたちに賄賂(ペイオラと言います)を渡していたのです。ジェームス・ブラウンはこの慣習を、ショウの宣伝にも活用することにしました。
もちろんDJたちは二つ返事で引き受けます。ジェームス・ブラウンの興行に協力したDJのラジオ局では、彼の曲がガンガン流れたそうです。
「髪が第一。次が歯だ。髪と歯。人にこの二つがあれば、すべてを持っているのも同然だ」
こうして彼は次々とショウを成功させますが、プロモーションよりも重要なのが当日のパフォーマンスです。
ジェームス・ブラウンは、身だしなみに大変な注意を払う男でした。何しろ、バンドメンバーは服が乱れているだけで罰金を課されるというほどです。前にも述べたとおり、アポロの店員にも衣装を配布するなど、そのこだわりは尋常ではなかったといえます。
「髪が第一。次が歯だ。髪と歯。人にこの二つがあれば、すべてを持っているのも同然だ」
彼のこだわりが端的に表現されているのが、この言葉ではないでしょうか。
日本でも90年代に、「芸能人は歯が命」という名キャッチコピーがありました。これはまさしく、ジェームス・ブラウンの価値観と一致しているといえます。
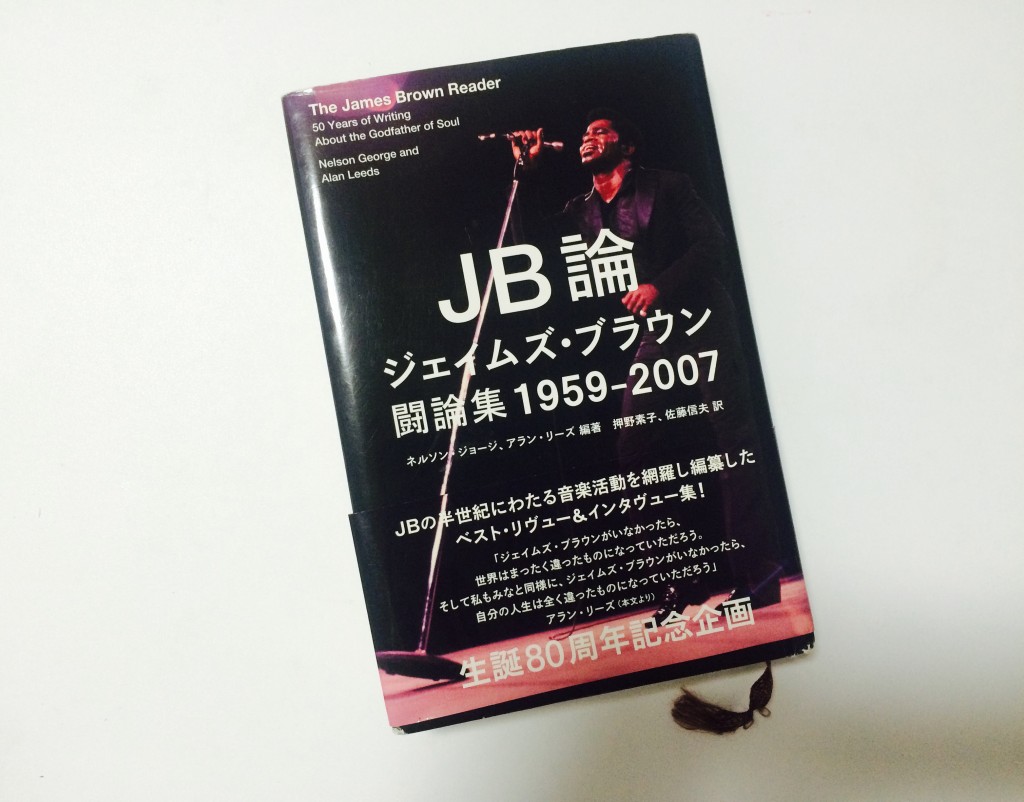 「JB論」ジェームス・ブラウン氏のインタビューなどを集めた大辞典。
「JB論」ジェームス・ブラウン氏のインタビューなどを集めた大辞典。
「楽に成功する方法などない。懸命に働いて、頑張るだけだ」
リスクを恐れることなく既存の価値観を破壊し続けたジェームス・ブラウンですが、彼が成功した理由は「バンドが最高」だったからだと、本人は言います。
斬新な曲も、売れないと言われたライブ盤も、興行システムの革命も、発想力と実行力が伴っていないと実現できない大きな仕事です。
しかしその大きな仕事に挑戦し続けている傍らで、「バンドのクオリティを常に上げ続ける」という最も基本的な原理原則と常に向き合い、練習を欠かすことがなかったのだといいます。
もちろん、罰金を課すほどの恐怖政治はバンドメンバーにとってポジティブなものではなかったようですが。
最後に、名言をもう一つ紹介して終わりにします。スティーブ・ジョブズもビル・ゲイツも、孫正義も松下庄之助もいい。けれど、死してなお私たちの魂を揺さぶり続けるショウ・ビジネスマン…ジェームス・ブラウンという人がいたということも、ぜひみなさんには覚えておいていただきたいなあと思います。
「楽に成功する方法などない。懸命に働いて、頑張るだけだ」
(JB論より引用)
おしまい